こんにちは!
神奈川県伊勢原市伊勢原にある、ゆめの森歯科いせはらです。
お子様の歯並びが気になる親御さんの中には、「遺伝が関係しているのかな?」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか?
確かに、歯並びには遺伝的な影響がありますが、それだけが原因ではありません。 じつは、日々の生活習慣やちょっとした癖が歯並びに大きな影響を与えることもあるんです。
そこで今回は、歯並びが遺伝する仕組みや、お子様の歯並びを守るためにできる対策などについてお伝えします。
お子様が笑顔でいられる未来のために、今できることを一緒に考えていきましょう!
遺伝で歯並びは悪くなる?父親と母親どっちに似るの?
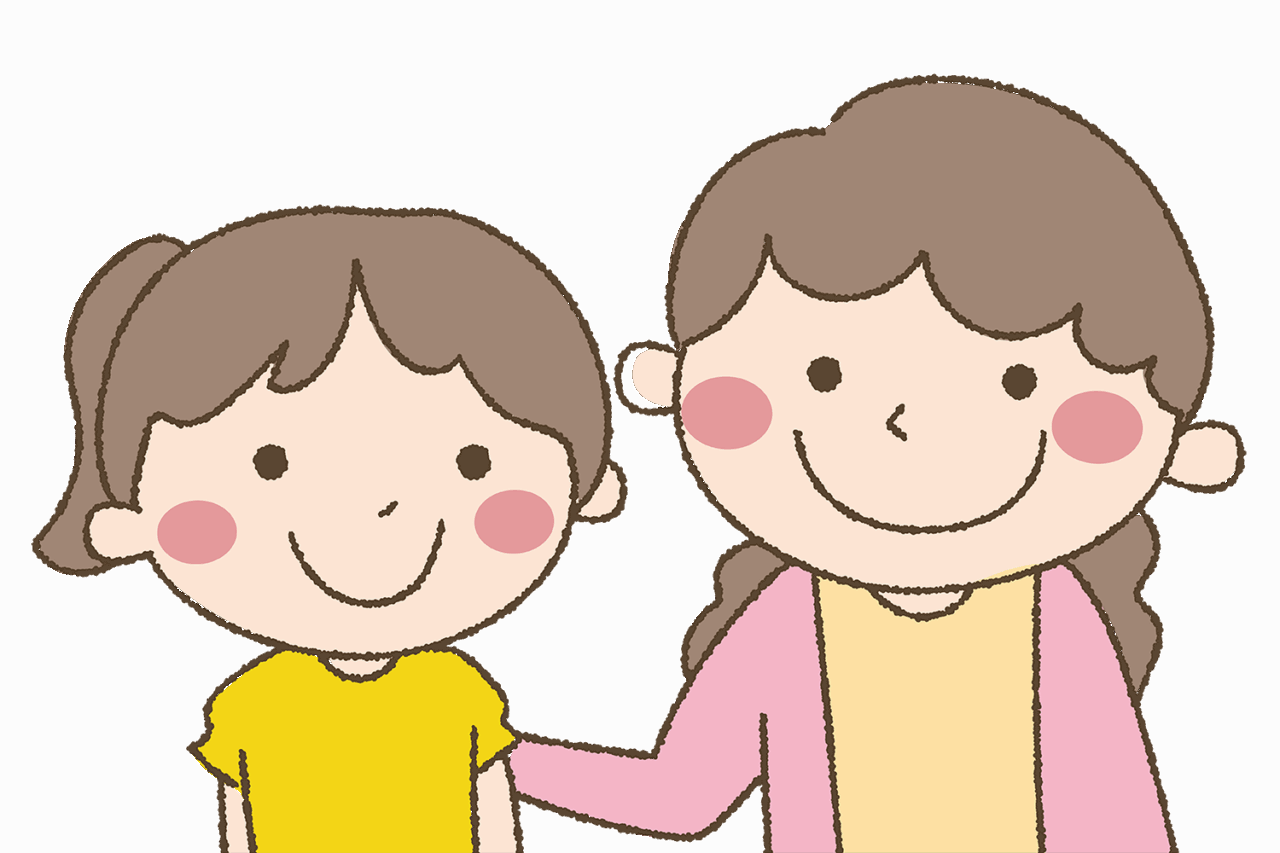
じつは、「出っ歯」や「受け口」など、遺伝的に引き継がれる確率が高まる歯並びがあります。また、歯や顎の大きさ・形に関しても、遺伝の影響を受けます。
これらのことから、お子様の歯並びは、親に似た歯並びになりやすいのです。
では、歯並びは父親と母親でどっちに似るのか?というと、容姿が「お母さん似」「お父さん似」となることがあるように、歯並びもどちらかに似ることが多いです。
ですが、歯並びが悪くなる原因のすべてが、遺伝的要因というわけではありません。
遺伝が影響している部分もありますが、それだけで決まるわけではなく、実際には生まれてからの環境や生活習慣などが影響して、歯並びが悪くなってしまうことがあります。
遺伝以外で歯並びが悪くなる原因は?どう対策すべき?
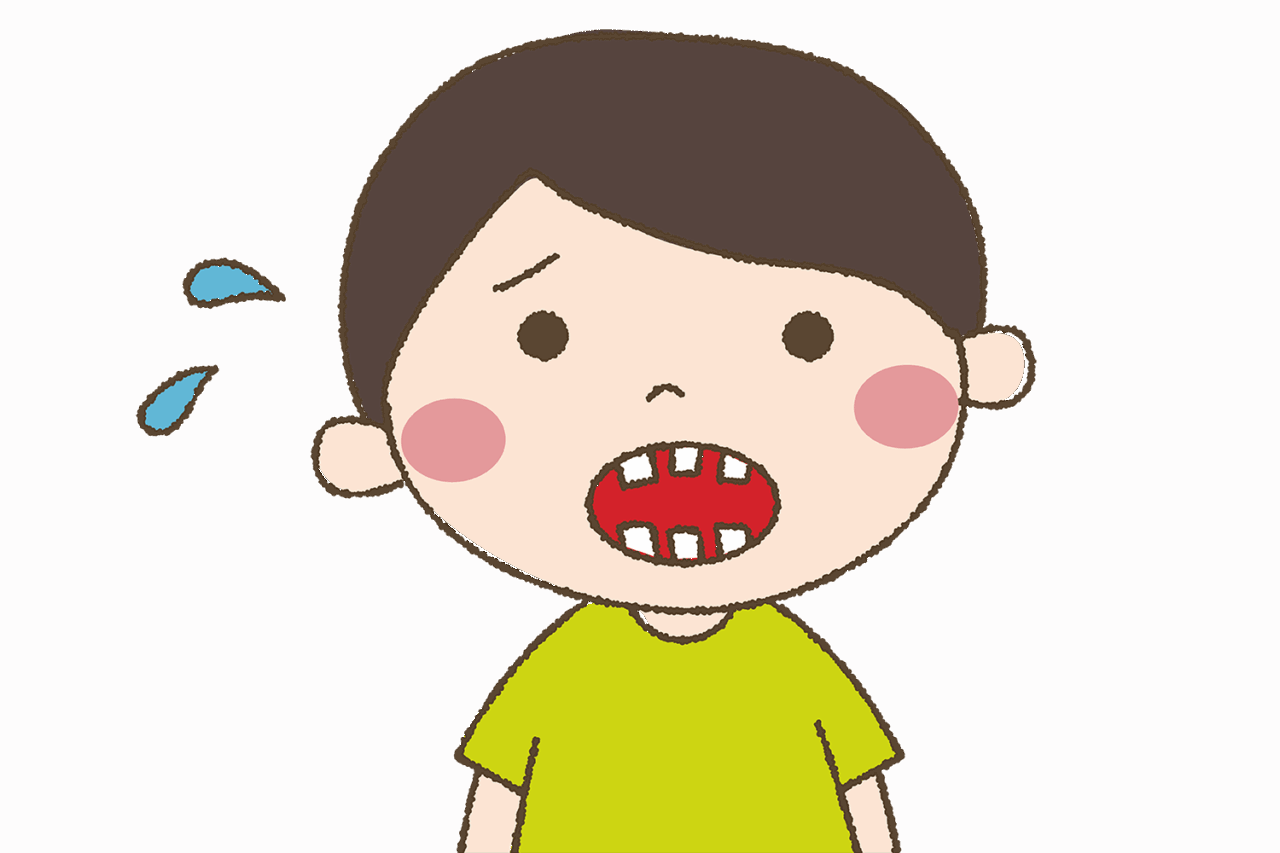
お子様の歯並びは、確かに遺伝の影響を受けますが、それだけではありません。毎日の生活習慣やちょっとした癖が歯並びに影響を与えることも多いです。
「こんなことで?」と思うようなことが、じつは歯並びに大きな影響を与えていることもあります。
そのため、まずは歯並びが悪くなる原因を理解し、お子様の歯並びを守っていく必要があります。
口呼吸
お子様が普段から、お口がポカンと開いていることはありませんか? もしそうなら、それは「口呼吸」のサインかもしれません。
口呼吸が習慣化すると、以下のようなリスクがあります。
| ・上あごの成長が不十分になり、歯がガタガタに ・唇の筋肉が弱くなり、前歯が前に出やすい(出っ歯になりやすい) ・舌の位置が不安定になり、正しい飲み込みや発音が難しくなる ・むし歯や風邪にかかりやすくなる など |
このような状態が続くと、お口の周りの筋肉がうまく働かず、食べる・飲み込む・話す・呼吸するといったお子様の大切な機能の成長が妨げられてしまいます。さらに、唇の力が弱まることで歯並びを整える自然な圧力がかからなくなり、前歯が前に出やすくなったり、上あごの発育が十分に進まなかったりする原因になることもあります。
「もしかしてうちの子、口呼吸してるかも…?」と感じたら、まずは口呼吸の大きな原因となる「鼻づまり」や「鼻炎」の有無をチェックしてみましょう。鼻の通りに問題があった場合には、必要に応じて、耳鼻科を受診する必要があります。
また、口呼吸を鼻呼吸に改善するには 「舌のサイズに合った上あごの広さ」も必要です。これは、舌が上あごにぴったりとくっつくことで、自然な鼻呼吸ができるようになるためです。
成長段階のお子様であれば、舌やお口のトレーニングを通じて顎を自然に広げることも可能ですが、それだけでは難しい場合もあります。
その際は、顎の発育を促すために、子どもの歯列矯正を検討することも一つの選択肢です。
お子様の口呼吸に早めに気づき、適切な対策をとることで、歯並びだけでなく健康を守ることにもつながります。
口呼吸を改善し
顎の発育を促すこどもの矯正
\ はこちら /

生まれてからの生活習慣
子どもの歯並びは、毎日の何気ない生活習慣によって、大きく影響を受けることがあります。
たとえば、こんな習慣が歯並びの乱れにつながることも… 。
| ・指しゃぶりを長く続けている(およそ4歳以降)…前歯に負担がかかり、出っ歯や開咬のリスクあり ・爪を噛む癖…出っ歯や開咬のリスクあり ・頬杖をよくつく…顎に偏った力がかかり、歯並びやかみ合わせのバランスが崩れる ・うつぶせ寝や横向き寝が多い…顎に圧がかかり、歯並びが乱れる原因に ・姿勢の悪さ…体のバランスが崩れ、口周りの筋肉や骨格にも影響 猫背は呼吸がしづらくなり、口呼吸につながることも |
子どもの癖って、つい「まぁいっか」と見過ごしがちですよね。
ですが、 日頃からちょっと意識してあげるだけで、歯並びのトラブルを防げることもあります。
生まれてからの食生活
お子様の食事内容や食べ方は、将来の歯並びに大きく関わります。とくに「しっかり噛むこと」は、顎の発達を促し、きれいな歯並びをつくるために欠かせません。
しかし、最近はパンや麺類などやわらかい食べ物が多く、噛む回数が減りがちです。このような食生活が続くと、顎の発育が不十分になり、歯がきれいに並ぶスペースが足りなくなったり、舌や口周りの筋肉が十分に育たず、正しい飲み込みができなくなったりすることがあります。
こうした問題を防ぐためには、食事やおやつに「かみ応えのある食材」を意識的に取り入れることが大切です。たとえば、根菜類や大きめにカットした食感のある食材を取り入れることで、自然と噛む回数を増やすことができます。
また、食事の内容だけでなく、食事環境や習慣も歯並びに影響を与えます。授乳の姿勢や離乳食の進め方が適切かどうか、食事中の姿勢は正しいか、椅子やテーブルの高さは合っているか、食具の選び方は適切かなど、細かな点にも注意が必要です。さらに、急かされた食事や孤食なども、しっかり噛む習慣を妨げる原因になります。
お子様の歯並びを守るためには、日々の食事の取り方や環境を見直すことが大切です。食生活について気になることがあれば、いつでも当院スタッフへお気軽にご相談ください。
乳歯の早期喪失
「乳歯はいずれ抜けるから、むし歯になっても大丈夫!」と思っていませんか? じつは、 乳歯がむし歯で早く抜けてしまうと、永久歯の歯並びに大きな影響を与えてしまう可能性があります。
たとえば…
| ・永久歯のスペースを確保できず、将来ガタガタの歯並びに ・隣の歯が倒れ込んで、かみ合わせのバランスが悪くなる ・しっかり噛めないことで、顎の成長にも影響が出ることも |
などの悪影響が出る可能性があります。
こうした問題を防ぐためには、「乳歯のむし歯を予防すること」がとても大切です。乳歯は一時的なものではなく、永久歯が正しい位置に生えるための大切な役割を担っています。
将来のきれいな歯並びを守るためにも、定期的に歯科検診を受け、お子様の乳歯をしっかりケアしていきましょう!
まとめ
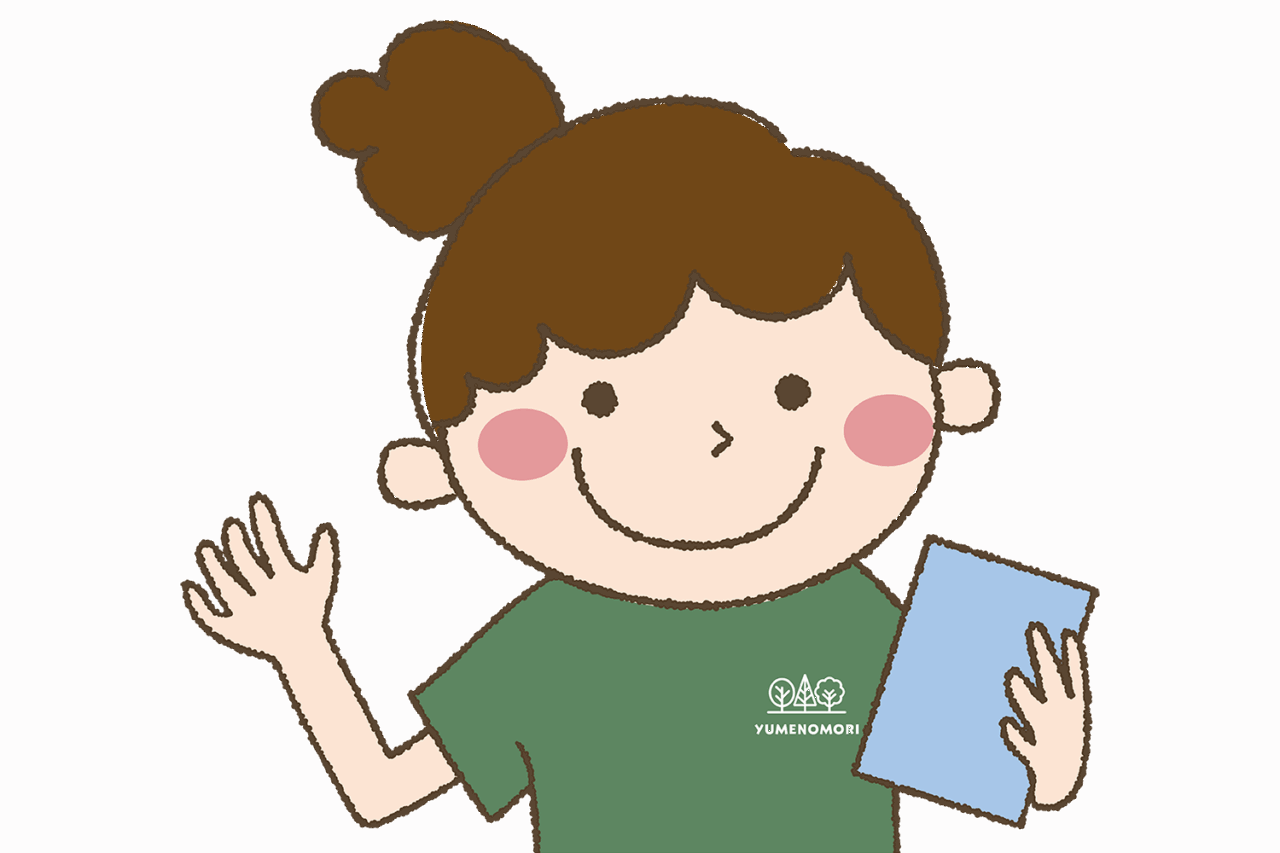
お子様の歯並びには遺伝的な影響があることは確かですが、それだけではなく、日々の生活習慣や癖も大きく関係しています。
お子様の歯並びを守るためには、早い段階で歯並びが悪くなる原因について知り、適切な対策を取ることが大切です。
当院では、お子様の健康的なお口の発育をサポートするため、日常生活の中で気をつけるべきことやアドバイスなどをお伝えしています。また、歯並びに影響を与えるお口の癖がある場合には、トレーニングを行ったり、顎の発育を促すためのこどもの矯正治療なども行っています。
お子様の歯並びについてご心配や疑問がある場合は、ぜひ当院にご相談ください。専門の歯科医師が、お子様の歯並びのチェックや、必要なアドバイスをさせていただきます。
日々のちょっとした心がけが、お子様の歯並びを守る大きな力になります。
お子様の健康な未来を一緒に支えていきましょう。当院がそのお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。





